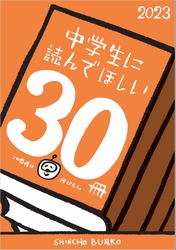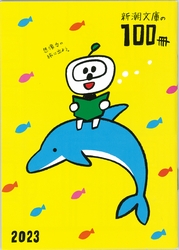 |
新潮文庫の100冊 (2023年) |
|||||||
|
|
||||||||
○配列
|
||||||||
|
|
||||||||
| ★新規採用作家 ●復活した作家 ▼交代した作家(#は10年以上継続して採用されてきた作家) |
||||||||
|
|
||||||||
| ○コメント 今年(2023年)のパンフレットも例年通りキュンタが描かれ、昨年(2022年)と同じく表紙にはサブタイトル「想像力の旅に出よう。」が記されています。黄色と青色が目立つ表紙のデザインは、昨年(2022年)のパンフレットと並べてみると雰囲気が似ています。 今年(2023年)は(久しぶりに・・・)キュンタがイルカに乗って海に出かける夏らしいストーリー展開です。おそらくこれは2023年5月に発表された(新型コロナウイルス感染に伴う)行動制限解除の反映なのでしょう。 今年(2023年)の「100冊」のオリジナルプレゼントは、昨年(2022年)同様「ステンドグラスしおり」(昨年(2022年)とは別デザイン)です。TwitterやInstagramを駆使すれば抽選で「純金キュンタしおり」(昨年(2022年)とは別デザイン)が当たるのも例年通りです(Twitterについては、あれこれ仕様変更が行われて従来ほど快適には使えないようです(2023年7月時点)・・・)。 今年(2023年)のパンフレットの構成についても昨年(2022年)とほぼ同じです。 今年(2023年)の「100冊」のWebサイトは昨年(2022年)と同様に過去のキュンタのストーリーやキュンタに関するフリーイラストページ、LINEスタンプ、「Tik tok」動画が開設されています。今年(2023年)の「100冊」のWebサイトでは新たに「書店さま向けフェア小冊子追加注文」の項目が設けられているのに気がつきました。2023年7月始めに近所や神保町にある何軒かの書店に立ち寄ったところ、どの書店でも(新潮文庫に限らず・・・)夏の文庫フェアの展開が例年と比べて小さく、各社のキャンペーン・パンフレットが目立たない置かれ方をしている印象を受けました。これは、今年(2023年)になって日常生活の各所でレシート等の紙の利用廃止の理由付けにされるDXやSDGs(+経費節減?)の反映なのでしょうか? 今年(2023年)の「100冊」は(私のカウント方法では)93人の作家の作品(97冊)が採用されています。昨年(2022年)は94人の作家の作品(95冊)の採用だったので、今年(2023年)は昨年(2022年)とほぼ同等といえそうです(私のカウント方法では加藤シゲアキ、村上春樹、ドストエフスキーについては2分冊を1冊としてカウントしているので、これらの分冊を別々にカウントするなら100冊になります・・・)。 今年(2023年)の「100冊」に関する作家の内訳をみてゆくと、新規採用作家(8人)、復活した作家(4人)、交代した作家(13人)となります(昨年(2022年)はぞれぞれ4人、10人、17人だったので、今年(2023年)は新規採用を多くする方針なのでしょう・・・)。 (私のカウント方法での集計結果ですが・・・)日本人作家の作品と海外作家の作品については、それぞれ80冊、17冊となり、全体に占める海外作家の作品の割合は18%になりました(ちなみに、海外作家作品の割合の推移はこちらにまとめてあり、最近10年間は14%〜20%の範囲内で変動しています)。 以下、今年の「100冊」のパンフレットを読んで気がついたことを記しておきます。
|
||||||||
| (文中敬称略) (2023.7.17) |
||||||||